歯科技工士に代わるAIが登場する未来が来るか?
AI時代の専門職としての人間力とは
2025年7月01日
インサイドフィールド 中野田 紳一
はじめに:技術とは何かを体系的にあつかうナレッジマネジメント
AIやデジタル技術の急速な進展によって、歯科技工の現場ではすでにクラウンの自動設計・自動加工が実用段階に入り、もはや人の手を介さずともほとんどの補綴装置はAIと機械加工による完全自動化生産が可能になる時代が目前に迫っているという、漠然とした実感がある。特に大規模言語モデルの出現などに伴い、「専門職としての歯科技工士は今後も本当に必要なのか?」という議論が、厚労省などでも活発になされている。この問いに向き合うためには、まずは歯科技工士の技術とは何かを、あらためて理解する必要があるのではないだろうか。
ナレッジマネジメント は、組織内に蓄積された知識を共有するための方法論であり、一般に「暗黙知」から「形式知」への変換プロセスがテーマである(1995)。過去、歯科技工学においても、熟練技工士の技能を数値化する潮流があった。匠の技を科学的根拠に基づく再現可能な技術として伝承できるよう、匠に内在する暗黙知をマニュアルなどの形式知として記録する努力がなされてきた。これはまさに、見えない術を言語化・数値化してきた歴史であった(2006)。
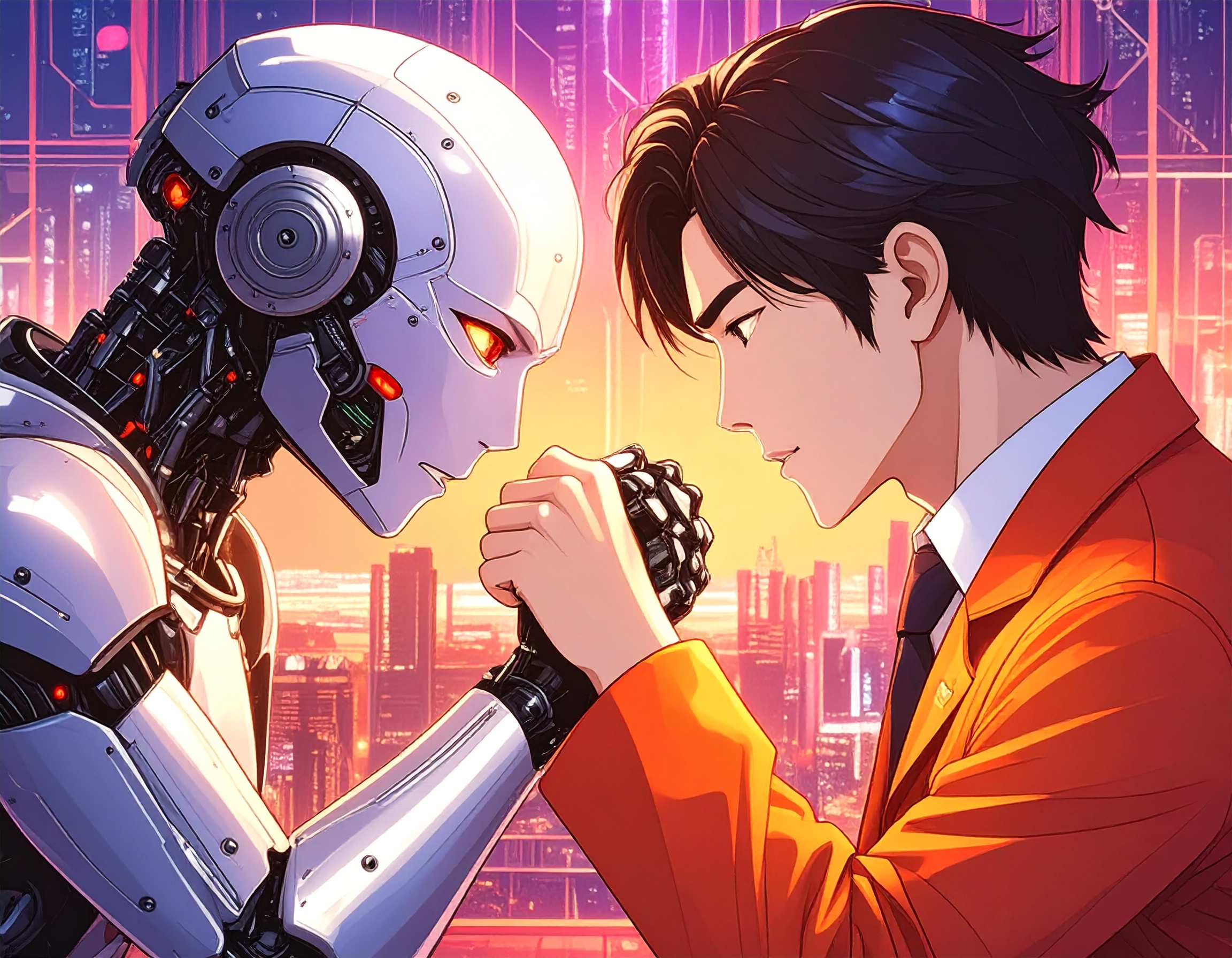
生成系AIによる本文のイメージイラスト
歯科技工に暗黙知がある限りAIは歯科技工士をこえられない
まずAIを効果的に活用するには、適切な「プロンプト(命令文)」と、そこに含まれる正確なパラメータ(=形式知)が不可欠である。大量の症例から得た数値、基準値(平均値)、素材特性値などがこれにあたる。すでにデジタルデンティストリーの進展に伴い、形式知としてのデジタルデータ(JPG、PDF、STL等)を正確に扱うスキル(=データベースエンジニアリング)の素養は、歯科技工士にとって必須の能力となりつつある。つまり、AIによるアウトカムは、臨床家たちが長年かけて蓄積してきた形式知の質と量に依存しており、これまで十分に構造化されてきた分野では、今後もさらに自動化が進むことになる。
一方で、歯科技工士の技術に残る「暗黙知」の量と質こそが、これまで以上に専門職としての歯科技工士の本質的な存在価値になる。ここでいう「暗黙知」とは、「嫌な予感」に敏感であることであり、「設計は妥当か」「臨床的に最適か」を評価し、修正や提案を行うといった、失敗の兆候を見抜く判断力=プロフェッショナルとしての力量を指す。つまり歯科技工には「AIに与えることができない暗黙知」が存在している以上、AIがすべての結果を正しく導き出すことはできない。つまり、このような「AIに与えることができない暗黙知」を瞬時に読み解き、膨大な情報から適切に判断する“塩加減”のようなセンスを磨くことが、歯科技工専門職の存在価値や、AIとの違いを明らかにする。
塩加減の「足りない理由や背景」と「もしも今、加減するとどうなるかを予測できる力」
たとえば、要介護期にはどのような仕様の義歯が適切か、そもそも義歯自体が必要かどうかといった議論において、“塩加減”がメタファである。すなわち、患者ごとの微妙な現場感覚を加味した“ちょうどよさ”を見極める判断力である。単に技術的に義歯を作ることができるかどうかではなく、「その方法が妥当なのか」「この方法は生命予後に有効か」を理論的に考えることができる能力が“塩加減”に含まれる。臨床現場では限られた医療資源を効率的に活用するために、緊急度や重症度に基づくトリアージ、トレードオフ、プライオリティの判断が日常的に行われている。歯科技工士が本格的にチーム医療に参画するためには、こうした判断の現場に継続的に関与し、体感的に経験する必要がある。高齢化が進む中、IoT技術を応用した遠隔対応可能な未来型補綴装置などの開発も視野に入れ、介護・福祉分野における多職種との連携が一層重要になる。そのためには、AIやDBを活用した情報共有支援環境を構築し、データサイエンス的・プログラミング的思考を取り入れつつ、“塩加減”とも言える暗黙知を継続的に磨いていくことが求められる。このように、歯科技工士の専門性を確立するために必要となるのがSE的視点であり、そのITリテラシー教育の刷新こそが、AI時代における歯科技工士教育改革(口腔工学科・情報マネジメント学,2025)である。
具体的には、診療方針や技術分野、患者の個性や社会的背景、治療目的や医療課題の本質などを共有できる環境を構築する力(データベース基盤型歯科技工:形式知を共有・活用するチーム医療による歯科技工)がその一つである。そのうえで、エビデンスや、臨床感覚に基づく判断を支援する環境を構築する力(データサイエンス連携型歯科技工:ゴールを共有し、分析によって臨床判断を支援する歯科技工)も、歯科技工士に求められる。さらに、広義の医療人としての立場を確立できるよう、単なる技工物の製作者を超えて、広く医療・介護・福祉における複合的課題に対応できるよう、センサー技術や電子機器と連携した装置を提供できる力(エレクトロニクス実装型歯科技工:予防や状態把握に貢献できる次世代型の技工物)も必要になってくる。このように、DB基盤型、AI・DX連携型、IoT実装型歯科技工の実践が、AI時代における専門職歯科技工士の価値を高め、未来を切り開く一助となる。
専門職の本質を支える2つの指向と、未来を切り拓く3つの力
【2つの指向:専門職としての根幹】-
コミュニケーション指向(チーム医療参画のための関係構築)
- 歯科医師や歯科衛生士との信頼関係を築く力。相手の立場に立って、対外的にオフィシャルなメール文を適切に作成できる文章力。また、必要に応じて生成系AIを活用し、自身の文章を改善・修正し、節度をもって自分の意見を提案できる能力。
-
臨床現場指向(患者の希望や術者の意図・治療のトレードオフを理解できる幅広い専門知識)
- 歯科医療全般への理解を基盤とし、医療機関で生じる課題やリスク、プライオリティーやトレードオフを共有できる現場感覚。また、患者の気持ちに寄り添うことができる、医療人としての感性。
-
データベースを構築する力
- チーム医療を実現するために医療情報を共有できる環境を構築することによって、形式知を共有・活用・管理する力。
- データベース基盤型の汎用CAD・CAM(デジタルデンティストリー)を扱える能力。
-
プログラミング的思考とプログラミングを実践する力
- AIやデータベース、汎用CAD(SDK)を活用し、科学的根拠と臨床現場の感覚に基づく判断を支援する環境を構築する力。
- チームでゴールを共有し、分析を通じて臨床判断を支援する、データサイエンス連携型の汎用CAD・CAM(デジタルデンティストリー)を扱える能力。
- 広く医療人として歯科チームに参画して、他科と協業して活躍できる力
- 広義の医療人としての立場を確立し、技工物の製作者にとどまらず、医療・介護・福祉における複合的な課題に対応できる力。
- プログラミングやネットワークを活用したセンサー技術や電子機器と連携する装置を提供し、予防や把握に貢献する次世代型の歯科技工を実現する能力。